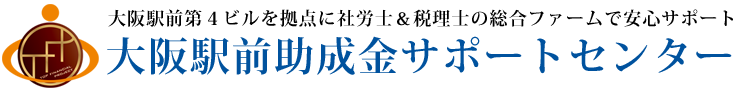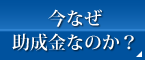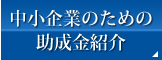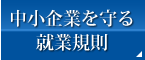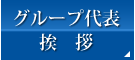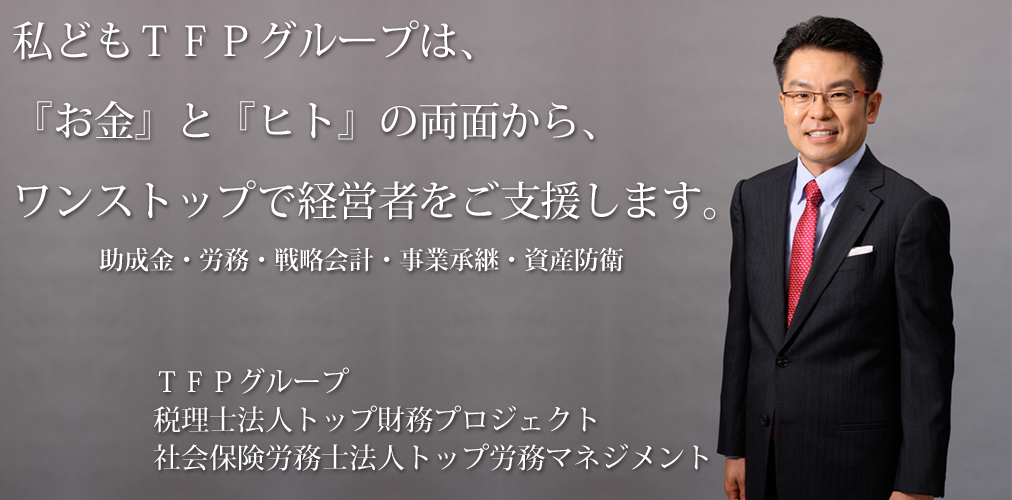働き方改革法は“見たくない現実”なのか?
2019年4月1日を振り返ってみると、新元号発表の日だけではなかった??
この日より『働き方改革関連法』が施行されました。
この動きを経営者は軽く見てはダメでしょう。
なぜなら、1947年の労働基準法制定以来、“70年ぶりの大改革”といわれるからです。
長時間労働や過労死の防止を目的に、敢えて罰則を付けてまで、
▼年次有給休暇制度の取得義務化
▼残業時間の上限規制
が盛り込まれたことが大きな特徴です。
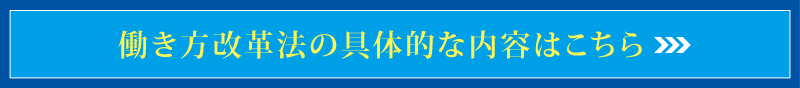
一方、経営者にとってはどうでしょうか?
人手がなかなか確保できない今日、ギリギリの人数でやっている。
それなのに「年休を取らせろ」「残業はさせるな」とは一体何事か!?
こんな法律ができたら、事業が成り立たないじゃないか!
そんな悲鳴が経営者から聞こえてきそうです。
働き方改革法はまさに“見たくない現実”と言えるのかもしれません。
しかし、よく考えてほしいのです。
「法律でこうなった以上、ちゃんと守らなければならない。ああ、仕方ないなぁ~」
という義務感だけの思考回路で終わらないでほしいのです。
確かにわれわれ士業にも責任の一端があるかもしれません。
士業が経営者の皆様からお叱りを受けるのは、杓子定規な回答で終始、法的な義務感だけを訴える対応です。
「税法ではこんな規定になっているので、こう処理しないとダメです。そうしないと、税務調査で否認されますよ。」
「労基法ではこんな定めなので、これではダメです。そうしないと、労基法違反で訴えられますよ。」
確かに立法趣旨は以下の通りです。
▼税法 = 税金を取るための法律
▼労働基準法 = 労働者を使用者から保護する法律
だからこそ、われわれ士業が義務感だけを訴える対応をしてしまうと…
「おたくは一体どこを向いて、 仕事をしているの??
税理士って、税務署の回し者? 社労士って、労働者の味方?
おたくにお金を払っているのは、 一体誰なのか、わかっているの??
法律上ダメかどうかぐらい、今のご時勢、ネットで調べたら、 すぐにわかる話でしょ。
私は別に脱税する気もないし、 労基法違反するつもりもない。
おたくに聞いているのは、 うまくリスクを回避するための知恵なんだよ。
それが聞きたいから、 顧問料を払っているんです。」
とお叱りを受けることになります。
(反省!)
:
:
:
2024年度より新紙幣が発行されます。
新千円札の顔になるのは、北里柴三郎氏。
『日本の細菌学の父』と言われた医学博士です。
北里柴三郎氏にこんな名言があります。
……………………………………………………
医者の使命は、病気を予防することにある。
……………………………………………………
今日の医学では『予防』の概念は、当たり前になっています。
しかし、明治から昭和初期の時代下で、北里先生は予防の意義をすでに説かれていた。
敬服の限りです。
医学のような高尚な専門領域には遠く及びませんが、
士業のわれわれもこの言葉を肝に銘じるべし。
そう自戒したいと思います。
答えは『働き方改革支援コース(人材確保等支援助成金)』を利用することです。

まさに今年度の新設助成金の目玉でしょう。
国は中小企業に対し、義務の履行だけを求めているわけではありません。
義務があれば、権利も存在します。
しかし、義務は黙っていても履行されます。
ただ権利は自ら手を挙げ、行動しなければ、享受できません。これは世の常ですね。
働き方改革法の趣旨をきちんと理解し、忠実に実行する中小企業においては、
自ら手を挙げ、助成金を獲得していかねばなりません。
井上礼之氏(ダイキン工業元代表)に、こんな名言があります。
……………………………………………………
今のように、変化が常態化した経営環境にあって、
変化に対応するだけでは、 予期せぬ競合相手に負けてしまう。
自ら変化を仕掛けていく、 攻めの姿勢を保つこと。
そこに徹底して、こだわるべきだ。
……………………………………………………
1994年からダイキン工業の社長に就任。
経営危機にあった同社を世界トップクラスの空調機メーカーに成長させた経営手腕。
当時と時代背景は異なりますが、 この精神は今日でも大いに学びになります。
働き方改革法を遵守する。
コンプライアンス経営は大変重要です。
しかし、井上礼之氏の言葉にあるように、働き方改革法に対しても、
「単に変化に対応するだけではダメ。 自ら変化を仕掛け、攻めの姿勢を保つ。」
という経営姿勢が今求められています。
『変化に対応する = 働き方改革法を遵守する』

▼働き方改革法の施行
⇒ 単なるコンプライアンス遵守の話で終わらせない
⇒ 新設の助成金を要マーク
⇒ 社員がイキイキ働ける職場環境づくり変革の大チャンス
⇒ 決して“見たくない現実”でなくなる
共に社長業を楽しみながら、組織の成長を目指しましょう。